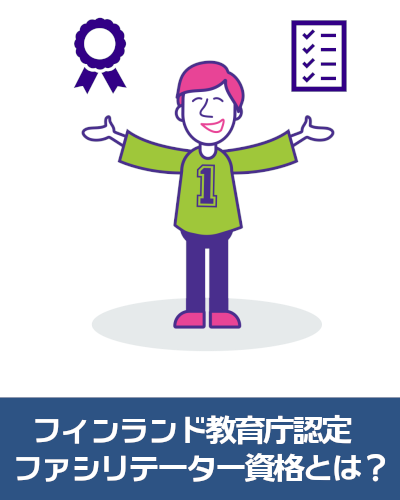フィンランド教育庁認定ファシリテーターの声
フィンランド教育庁認定ファシリテーター1期生

溝江直樹さん
SMBCラーニングサポート株式会社
感情にフォーカスするファシリテーションの深さ
対話の進め方に重きを置くファシリテーターの姿勢を学べました。
参加者の感情を大切に扱うことにより、ひとりとして置き去りにしないPepeの姿勢に感銘を受けました。
仲間と学ぶ楽しみ
フィンランド式ファシリテーション®をマスターするのは半年かけての長い学びでしたが、ポジティブな仲間と共に楽しい時間を過ごせました。特に、認定試験に向けてチーム一丸となってワークショップを設計しましたが、その過程が楽しくてたまりませんでした。試験当日も、試験への緊張感より楽しさが勝りました。ワークショップを仲間と一緒に成功させようという思いが楽しさを生み出したのです。
心理的安全の高い場づくりができていると感じます
フィンランド式ファシリテーション®で学習したことはグループのミーティングで使ったり、研修やワークショップの設計にも活用しています。その結果、仲間や参加者も自由に発言できるようになり、関係も良くなり、心理的安全の高い場づくりができていると感じています。先日、ミーティングの仕方についてミーティングをしたところ、運営方法が大変好評でした。
より深い学びができた受験プロセス
フィンランド教育庁認定ファシリテーター資格を取ったのですが、受験までのプロセスがとても有意義でした。今まで学習したことを振り返り、仲間と一緒になって企画をするプロセスを通じてファシリテーションをより深く理解できたと思います。また、仲間との絆も生まれました。

松嵜恵子さん
損害保険ジャパン株式会社 人事部 人材開発グループ

鈴木勇次さん
カレイドファーム 代表
組織開発コンサルタント/国際コーチング連盟認定プロフェッショナルコーチ
フィンランド教育庁認定ファシリテーター/フィンランド式ファシリテーション®トレーナー
チームで学べた
一緒に学んだ方々とのチームラーニングのお陰でとても学びが広く深くなりました。
素敵な仲間が増えたのがうれしいです!
認定試験
グループで実際のファシリテーションを企画、設計、実施をしました。これをすることによってファシリテーターに求められる8つのコンピタンシーの本当の意味が分かるようになりました。また、求められるレベルを実際に行うことで学びました。
試験後に貰えたフィードバックを基に、改めて振り返って学ぶことで更にそれが身に付いたと思います。
「大人の学びはアウトプットから」と聞いた事がありますがそれを実感しました。
対話の質が格段に上がります
私は企業での研修講師をしています。
ある企業の社長さんが、「うちの社員は話さないから場がもたないかも」とおっしゃっていたのに、実際にフィンランド式ファシリテーションで対話してみると「こんなにみんな話すんですね!」と驚かれて。
普段あまり話さない人でも自然と話し出せる場がつくれるのが、この手法のすごさだと思います。
大学講義での活用と変化
私は、大学で講義もしています。その大学の講義でも、フィンランド式ファシリテーションを取り入れてから大きな変化がありました。
「この授業が一番楽しい」と言ってもらえることが増えたのです。
理由を聞くと、「いろんな人と話せる」「共感や気づきがある」「自分にはないアイデアに出会える」といった声があり、関係性が深まり、場が変わっていく実感があります。
一例を挙げると、授業の冒頭で、CSAモデルの「C(共通のめざす姿)」をみんなで対話して共有するんです。「これを目指そう」とクラス全体で決めてからスタートすることで、学生たちのモチベーションがとても高い状態になるのを感じています。
「今日はどんな授業になるのかな」とワクワクしながら参加してくれる学生が増えてきて、「この授業が本当に楽しみなんです」「行きたい授業なんです」と言ってもらえることもありました。
その変化が、何よりうれしいですね。

犬山奈保子さん
コーリングラボ 代表
人財・組織開発コンサルタント
フィンランド教育庁認定ファシリテーター/フィンランド式ファシリテーション®トレーナー
フィンランド教育庁認定ファシリテーター2期生

波多野誠さん
独立行政法人国際協力機構(JICA)
ファシリテーションで深い対話をするための型が身につく
これまで様々なファシリテーション手法を学んできましたが、フィンランド式は、設計しやすい標準的な流れと深い対話をするための工夫があり、まさにシンプル、でもパワフルで実践的なファシリテーション手法を身につけることができました。職場内外の様々な場で活用していきたいです!
仲間との学び合い・ネットワーキング
公開コースに参加した方々との実践的なワークショップを通じて、オンラインでも対面でも良い学び合いができました。一緒に認定試験を受講したメンバー間でポジティブなフィードバックをし合い、フィンランド式ファシリテーション®を実践して広げていきたいという仲間ができたことも良い機会でした。
出会えてよかったフィンランド式
フィンランド式ファシリテーション®に出会い、ファシリテーションへの抵抗感がほとんどなくなりました。
学べば学ぶほど「チームでのワークショップを企画し、ファシリテーターとして振る舞うこと」が楽しくなりました。
私は、いくつかファシリテーションの研修を受講しましたが、フィンランド式は突出して使いやすい。シンプルかつパワフルだと思います。
認定試験の経験が大きな学びに
フィンランド教育庁認定ファシリテーター資格の準備から取得に至るまでが、本当によい経験となり、大きな学びにつながりました。
試験の準備段階では、限られた時間の中で、ワークショップを作り上げなければなりません。
素敵な仲間と、書籍やテキストを何度も見返し、理解の浅さを痛感しつつも、丁寧に議論を重ねてゆきました。
大変でしたが、楽しかった。

足羽崇さん
SIerのHR本部 人財開発部

末富真弓さん
GoodQuest代表 See the Good!アンバサダー
"合意形成"の在り方
一人ひとりの声を丁寧に拾い上げ、それを全体の合意形成へと収斂させていくという考え方とプロセスにとても共感しました。自分だけでは思いつかないアイデアが生み出されるのが醍醐味です。
活用の幅は広く、子ども達にも!
子ども達が学校内外において話し合い、合意形成をしていく場面はたくさんあります。個々の声を大事にするフィンランド式ファシリテーション®は、心身の発達差が大きい子ども達にもとても有効だと感じています。
研修やワークショップの設計が容易に!
フィンランド式の魅力はシンプルなストラクチャーと場に応じた様々なツールが用意されていること。私は、組織開発の研修やワークショップを設計したり、ファシリテートしたりすることが多いのですが、フィンランド式と出会ってから設計が楽になりました。また、一人ひとりの知恵を引き出し、お互いの考えを理解しながら合意形成をしていくため、参加者の納得度もとても高くなっています。
学びの仲間との繋がり!
フィンランド式を学びにくる仲間は、皆チームを、組織を、クライアントのコミュニケーションを良くしたい!という想いのある方ばかり。お互いに研鑽しあう関係性があります。1&2期のメンバーを中心に、『フィンランド式ファシリテーション®広め隊』が発足。資格取得後も高め合えるネットワークが素敵だと思います。

鈴木愛子
サクセスポイント株式会社 ポジティブ組織開発コンサルタント
フィンランド教育庁認定ファシリテーター3期生

粟田浩史さん
SOMPOビジネスソリューションズ
刺激的な仲間と体系的に学べる
ファシリテーションを体系的に学び、使いこなせるようになるこのコースは貴重です。共通点はただ一つ「ファシリテーションを学びたい」、さまざまなバックグラウンドを持つユニークな仲間との学びは刺激に満ちています。
シンプルでパワフル、だれも置き去りにしない
フィンランド式ファシリテーション®は、シンプルでパワフル、実際に使ってみるとその使い勝手の良さが実感できます。また、意見をまとめていく過程で誰も置き去りにしないさまざまな仕掛けは、ワークショップ終了後に大きな差を生みます。
ファシリテーションの奥深さを感じる学習機会でした
これまでに日常業務における日々の会議体やイベント運営など何気なく進めていました。しかし、フィンランド式ファシリテーションを学ぶことによって、より体系的・構造的に整理できました。学習後の会議運営はより合意形成しやすく、成果に繋がると実感しています。
では、なぜ成果に繋がりやすいのか?これはフィンランド式ファシリテーションが、極めて「シンプル」に設計されているからです。難しいワークショップの設計をしても参加者全員が腑に落ちた進行ができなければ成果は出ません。フィンランド式ファシリテーションを導入することで、対話が活発になり、誰もが納得できる合意形成を図れる。このファシリテーションは無限の可能性を秘めているなと実施するたびに感服しております。
切磋琢磨できる仲間の存在
試験に参加するに当たり、たくさんの仲間たちと切磋琢磨して臨みました。1時間弱のファシリテーションに何日も何日も議論を重ねて設計する際は、とてもかけがえのない時間だったと思い返しています。やはり仲間の存在はとても大きいと思います。

田代明久さん
株式会社パフ
専門役員

川崎博文さん
本田技研工業株式会社
誰もが参加できる対話型のファシリテーション!
日本には教育機関がたくさんありますがファシリテーションを学べる場は限られています。その中でも対話型という手法で実務的なファシリテーションを教えてもらうことができました。常に能動的に対話を通じて合意形成までの過程に参加する手法なのでワークショップ後に感じる参画意識・充足感は非常に高いものでした。
参加メンバーは多種多彩で刺激的!
参加メンバーは、経営者・専門職・会社員など多種多彩なメンバーでした。受講のきっかけはそれぞれですが皆さん問題意識をもって参加されていて非常に刺激を受けました。受講後もリピーターが多いのも『フィンランド式ファシリテーション®』の効果を各職場で実感しているからだと思います。
会議が終わった後の何とも言えない空気が一変!
いくつかファシリテーションの研修を受けたけど、なかなかその効果を感じれることはありませんでした。初めてフィンランド式ファシリテーションの講座を受けて、自身も社内のメンバーもその効果を体感し、ビックリしました。
社内では『そもそも会議なんて上から降りてくるもの、下から上げる提案に関しては重箱の隅をつつくようなもの』なんて声もあったけど、体感した後は言うべきことを言う、みんなが納得しているということ、そしてみんなが同じ方向を向いてることを大切する雰囲気になってきました。同じ会社で働く仲間としてこんなに嬉しいことはありません。
まだまだ教えて頂いたものを全部使えているわけではないですが、本当に学んでよかったと実感しております。

出澤雅司さん
株式会社美和建装
経営企画室 代表取締役
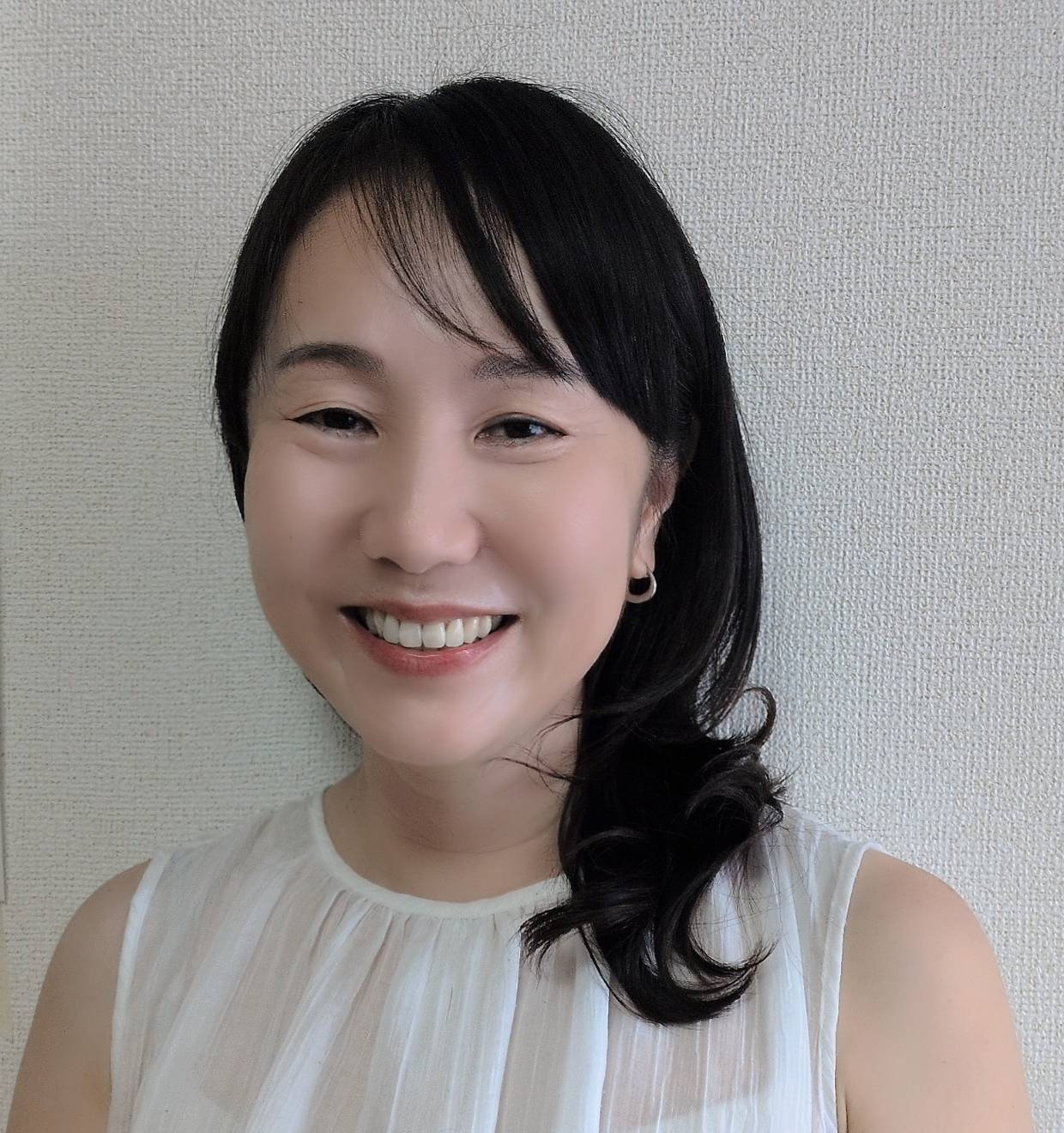
岩見香織さん
教育サービス業
営業統括本部/プロジェクトリーダー
「仕切らなくていいんだ!」──場に委ねる安心感
フィンランド式ファシリテーション®を学んで、まず感じたのは、「自分がすべてを仕切らなくていいんだ」という安心感でした。
フィンランド式ファシリテーション®を知る前は、悩みました。合意形成をするときにどのように意見をまとめればいいのか考えるのが苦しかったのです。しかし、フィンランド式ファシリテーション®を知ってからファシリテーター一人が頑張るのではなく、参加者全員を巻き込みながら進めるプロセスを適用すればいいのだとわかりました。これで肩の荷がすっと軽くなりました。それが、この手法の大きな魅力です。収束するプロセスが明快だからです。
また、Me-We-Usのステップを使えば、誰一人取り残されることがなく、全員が「聴いてもらえた」「自分の考えを言えた」と実感できます。その結果、参加者が自信を持ち、肯定感が高まる様子がはっきりと見えてきました。
進め方もシンプルで構造的なので、導入しやすく、安心して使えるのもポイントです。特に、場の中で自然と参画意識を引き出せるところに、フィンランド式ファシリテーションの力を感じています。
話したくなる場に変わる!──現場で起きた変化
私は、企業内で各種研修(階層別研修、入社前研修、コミュニケーション研修、雑談力研修、主任昇格時研修など)を企画・実施する立場にあります。
これまでもそれなりに研修を組み立てていましたが、フィンランド式ファシリテーション®を研修に取り入れるようになってから、参加者の反応が変わりました。今では、誰もが自分の意見を話し出し、互いの考えに耳を傾け、自然と学び合いが起こるようになりました。参画意識がぐっと高まり、対話の質も上がっていると感じます。
ファシリテーターとしてのあり方に変化
自分自身のあり方も変化しました。以前は、「自分がちゃんと進めなきゃ」と肩に力が入っていて、発散と収束の間で迷うことも多く、予定通りに進めることに意識が向いていました。
でも今は、プロセスを信じ、場に委ねることができるようになりました。まさに「手放す」ことの大切さを体感しています。
声を引き出す“対話の構造”が、医療現場に変化を生む
―本音が出にくい職場でこそ、フィンランド式ファシリテーションが活きる―
医療の現場では、上下関係や「空気を読む文化」によって、本音が出にくくなる場面が多くあります。
そんな現場で研修や人材育成に関わる中で、「どうすればもっと一人ひとりの声を丁寧に引き出せるのか」という問いを持ち続けていました。
フィンランド式ファシリテーションを学んでいくうちに、この手法がまさに現場での対話に役立つものだと実感するようになりました。
「事実・感情・意味・行動」の四つの質問を使った対話の設計や、CSAモデルをベースにした対話の流れは、研修やワークショップの中でも自然な気づきと相互理解を引き出してくれます。
また、「フェールメーター」などを用いたエネルギーの可視化も、場の状況を捉えるうえで非常に有効です。
混乱の中に「つながり」を生み出す、四つの問いのちから
―被災地での医療支援に活かされた、ファシリテーションの可能性―
この手法の真価を実感したのが、2024年の能登半島地震の現場でした。
医師として被災地に入り、医療チームをまとめる役割を担う中で、支援にあたる仲間たちが気持ちを言葉にできる場の必要性を感じ、四つの質問を使った対話の場を実施しました。
混乱の中でそれぞれが抱える思いや不安を言葉にすることで、チームに落ち着きとつながりが生まれていくのを実感しました。
ファシリテーターが仕切るのではなく、「構造」によって自然と声が引き出される。
この「対話の設計」の力は、私自身のリーダーシップの在り方にも影響を与えてくれています。
医療現場のように時間も人も限られる環境でも、「対話の構造」があることで場は確実に変わります。
一人ひとりの声が尊重され、ケアする側もケアされるような対話の場を、必要としている方にこそ、この学びを届けたいと思います。

北原佑介さん
たのはたラボ代表
研修講師/ワークショップデザイナー/救急医

宮崎宏興さん
NPO法人いねいぶる 理事長
NPOこそファシリテーションが必要
医療や福祉の現場は1対1の支援が多いですが、その先には必ず社会があります。世代や病気の有無、働いているかどうかなど、多様な人が関わる場だからこそ、ファシリテーションが欠かせないんです。
紙と鉛筆があれば、話し合いは始められる。準備されたワークショップももちろん大事ですが、公民館でのお茶や雑談の時間にこそ、一番価値ある対話が生まれることがある。そこにファシリテーションの技術を持った人が一人いるだけで、場の質が大きく変わります。
フィンランド式を学んで得たこと
Me-We-Usのステップを繰り返すことで、参加者が自然に学び合える。短時間でも深い学びに到達できるのは大きな強みだと思います。自治体の会議でもできる/できないの押し付け合いではなく、思考が深まる議論になりました。
準備万端で臨むこともできるし、即興でも裏紙と鉛筆と壁さえあれば場が始められる。この柔軟さは、地域やNPOの現場にとても合っていると思います。
学ぼうとする人へのメッセージ
私はフィンランド式ファシリテーションを学んで、自分が日々やっていたことを形として理解しながら進めることができるようになりました。なんとなくやっていたステップが、理由を持って設計できるようになりました!
これから学ぶ方も、既に実践している方も、学ぶことで自分の場づくりがより深まると思います。NPOの活動や地域の現場でこそ役立つ力になるはずです!
フィンランド教育庁認定ファシリテーター4期生

山口智江さん
損害保険ジャパン株式会社
千葉保険金サービス部
メンバーの当事者意識を高めるリーダーシップ
組織のマネジメントにおける「対話型リーダーシップ」の重要性は理解しているものの具体的にどのような取組を行ったらよいかを模索していたときに「フィンランド式ファシリテーション」に出会いました。
学びながら自分の組織の会議を「フィンランド式ファシリテーション」のツールを取り入れたものに変えていくことで大きな組織であっても対話が生まれ、メンバーの当事者意識が高まりつつあることを実感しています。
共に受験する仲間から刺激を受けました
認定試験においては、どんなツールを使えば効果的なのか、どんな問いを立てれば参加者が迷いなく対話できるのか、などについて準備段階から深く考えることができました。
なにより共に受験する仲間から多くの刺激を受け、そのつながりはかけがえのないものとなったことに感謝しています。
試験は“学びの場”
フィンランド式ファシリテーション®は、参加者同士がお互いを尊重しながら、自由にアイデアを出し合えるように工夫された、実践的でわかりやすいアプローチだと感じました。
今回の認定試験は、これまでの自分の実践を試すチャンスでありながら、新しい気づきもたくさん得られる場でもありました。説明会でPepeが話してくれた「試験は学びの場」という言葉がとても印象に残っています。仲間と一緒にワークショップを設計したプロセスは、まさに“学び合いの場”。試験後にいただいたフィードバックによって、自分の強みと課題を改めて認識できたことも大きな収穫でした。
対話で広がる可能性
試験での学びをさっそく職場で活用し、「対話」をテーマにしたワークショップを実施しました。場づくりの工夫やツールの使い方が、対話の質をグッと高めてくれることを実感しました。一緒に受験した仲間たち、そしてサポートしてくれたMaxさんやあいちゃんの存在は、本当に心強かったです。このつながりは、自分にとって大切な宝物。これからも仲間と学びを深めながら、現場でより良い対話の場づくりに活かしていきたいと思います。

大河雅治さん
株式会社文方社
コミュニケーション企画室 室長

田中達也さん
IT企業
DesignOps/Manager
私にとっての「フィンランド式ファシリテーション®」とは?
フィンランド式ファシリテーション®は、単なる進行技術ではなく、その人自身のスタンスや生き方に深く関わるものだと感じています。
参加者同士が経験を重ね合い、共に創発していくプロセスを通して、自然と変化への合意が生まれる。
そうした「対話の力」を信じて、誰もが本来持っている創造性を発揮できる場をつくることができる手法だと思います。
ユニークで深い学び
業界や職種、年齢の異なるリーダーたちと学び合う中で、視野が広がるとても刺激的な時間でした。フィンランドで組織開発に実績のあるGrape Peopleと、日本で場づくりに力を注ぐサクセスポイントが手を組んでいるからこそ体験できる、ユニークで深い学びがありました。
ファシリテーションは、集合天才を実現するための必須要素
VUCAの時代、企業の生き残りに、イノベーションが必須です。
過去は、天才的な個人が、イノベーティブな成果を創出することも多々ありましたが、近年は個人のつながりを強化し、チームでイノベーティブな成果を創出する時代に、なっています。
こんな時代においては、ファシリテーターだけが、ファシリテーションをできるだけでなく、イノベーションに関わる全ての人に、ファシリテーションを知ってもらいたいと思っています。
「習う」と「実践する」の大きな違い
試験までに、習ったファシリテーションスキルを使うことがありましたが、それは「使っているつもり」になっていただけだと気づきました。
試験では、ファシリテーションスキルを正しく使えているかが、問われ、自身の理解不足を痛感しました。
全員参加で課題解決
仕事現場で起こりがちな「声が大きい人の意見が通る」では、間違った意思決定をしてしまったり、優れた少数意見や新しい意見があっても、それが採用されなかったりします。また、言語化が不足した状態で、発言され、それが誤解を生んだりもします。
このようなことを防ぐために、ルールなしで議論を始めるのではなく、MeWeUsを活用しています。MeWeUsの活用が、組織に定着しているか?と問われると、まだまだ不足していますが、使い続けることにより、徐々に浸透していくと思います。
これから受験を考えている方へのメッセージ
日ごろから、ファシリテーションは実践してください。
ファシリテーションを学んだだけでは、ファシリテーションを実践できません。
ファシリテーターがプロセスに関与するには、ツールの使い方を知っているのはもちろんのこと、目の前で進行している議論の内容を、ロジカルに理解したり、コーチングスキルを使って、意見を引き出したり、様々なスキルを駆使する必要があります。
ですので、自身がファシリテーションをする立場にない会議においても、「自分ならこうする」を常に意識することが大切です。
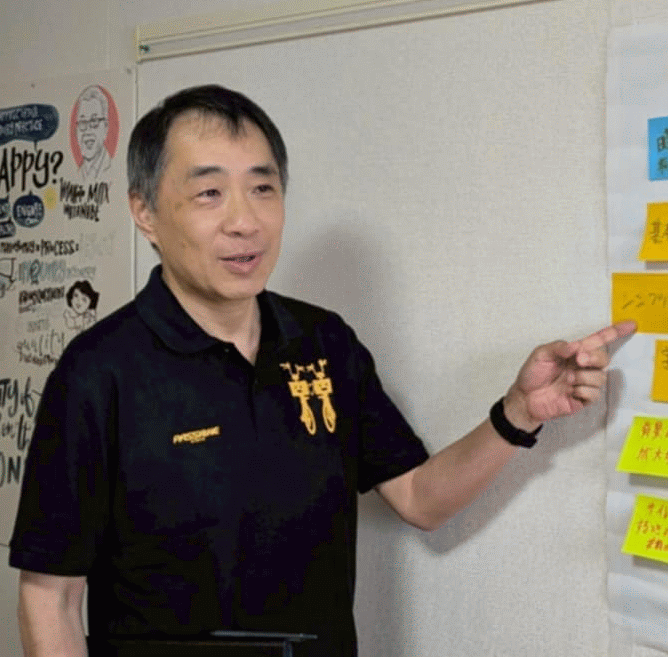
石田克英さん
電子部品製造会社
開発研究所 開発企画部 次長
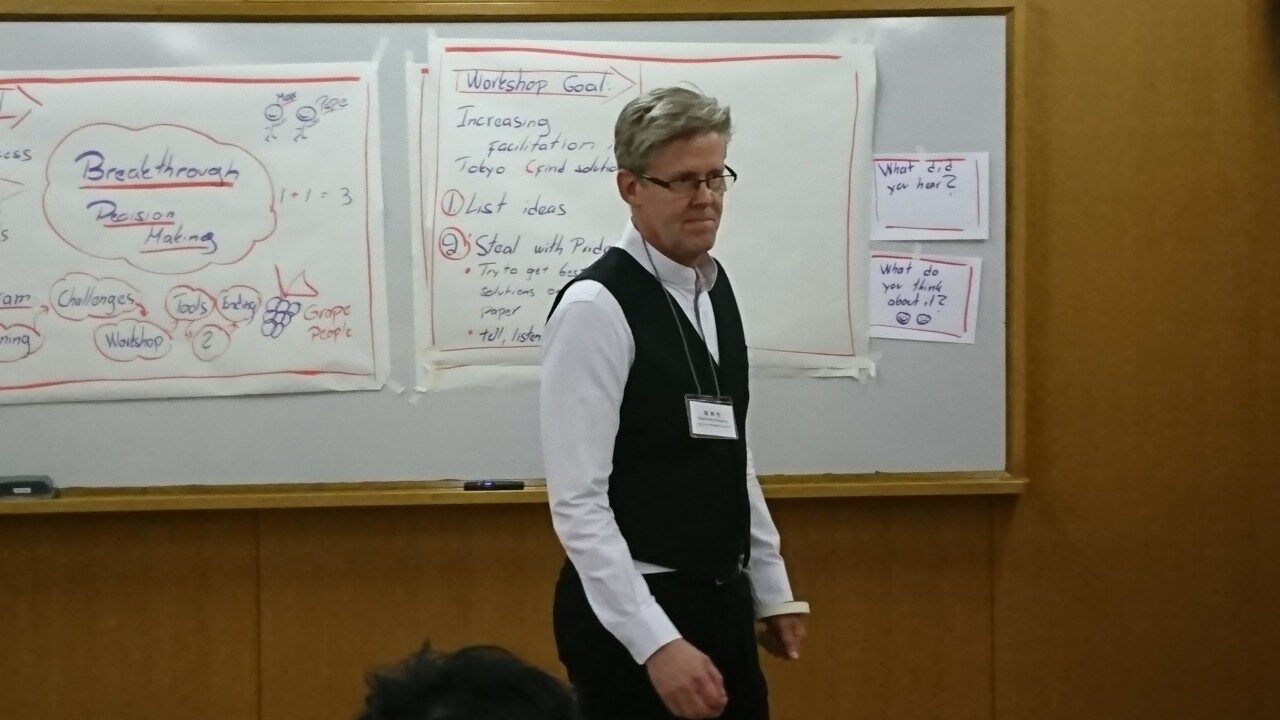
認定ファシリテーターの活用事例集
フィンランド式ファシリテーション®を具体的にどのように活用しているのか、どのような場面で役に立つのかについて、具体的な事例を認定ファシリテーターの皆様に聞きました。
インタビューや座談会の動画と合わせて具体的な活用事例をご紹介いたします。