認定ファシリテーター活用事例:山口智江さん
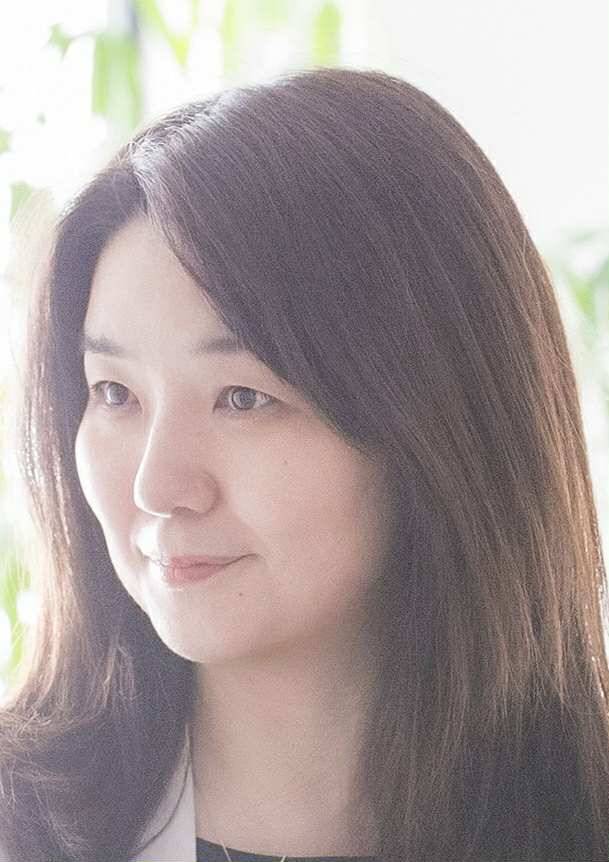
マネジメントやチーム運営、日常の小さな場面でも、人と一緒に物事を進めるときに役立つスキルです
山口智江さん
Tomoe Yamaguchi
損害保険ジャパン株式会社
千葉保険金サービス部 部長
プロフィール
損害保険ジャパン株式会社千葉保険金サービス部 部長。千葉県全域の自動車保険の保険金支払い業務を統括している。部内の会議や研修の場をファシリテーションで変革する取り組みを進める。フィンランド教育庁認定ファシリテーター。
こんな場で使っています
個人の思いを組織のパーパスに反映
部門のパーパスを作る際、まず個人のパーパスを見直し、チームミーティングで共有。その後、チームの代表者2名が中心となり、半日かけて部としてのパーパスを決定するワークショップを実施しました。個々の考えの意味をみんなで議論しながら言語化・可視化することで、パーパスを自分ごととして受け止める機会となりました。
経営計画作りへの活用
決定した部門パーパス「あなたの味方であり続ける」を基に、顧客・チーム・関係者など全ての対象に向けた経営計画を策定。各チームで進捗を共有し、大きな課題は部全体でフィンランド式のフレームワークに基づき議論することで、抜け漏れなく計画を体系化できました。
前向きな議論とチームの協働意識の向上
進捗報告では、できたことや通常業務の中で達成していることを意識的に取り上げることで、ネガティブな指摘に偏らず、意見が出やすく前向きな議論が増加。チーム全員の知恵を引き出し、計画の実行につなげるサイクルが生まれ、協働意識や主体性の向上にもつながっています。
楽しく、動きのある参加型ワーク
ワークショップ中は、付箋や絵を使った可視化や、ゲーム感覚でのやり取りを取り入れることで、参加者16名全員が楽しみながら主体的に関わる雰囲気が生まれました。楽しい経験が組織への理解や納得感の深化に寄与しています。
フィンランド式ファシリテーション®を学んだきっかけ
従来のトップダウン型ではなく、会話を重視したマネジメントが必要だと感じていました。会社としても1on1を導入するなど変化は進んでいましたが、会議の場は旧来型のまま。特に毎月の課長会議は「形式的に発言して終わる」もので、納得感や意味があるのか疑問を持っていました。
会議を変えるためには、進め方そのものを変革する必要がある。そう考え、ファシリテーションを体系的に学ぶためにフィンランド式を選びました。
フィンランド式ファシリテーションとは
旧来の会議は、参加者がパソコンを開きながら形式的に発言し、会議後には「何を決めたのか思い出せない」という状態でした。フィンランド式では、全員が時間内にしっかり考え、意見を共有し合います。付箋や模造紙を使って動きながら考えるため眠くならず、印象にも残ります。
一度その違いを体感すると、会議が楽しみになります。会議が単なる報告の場ではなく、深い対話の場に変わることが大きな価値だと感じています。
実際の活用シーンと変化
まず課長会議をフィンランド式に切り替えました。準備段階で、従来のやり方に満足しているかどうかを「ME-WE-US」でディスカッションしたところ、参加者自身が問題を自覚。4月から新しいやり方に移行する土台になりました。
導入初回は「面倒なことを始めた」と感じる課長もいましたが、実際にやってみると「達成感がある」「普段言えないことが言えた」「人の話を聞けた」と肯定的な感想が多く、その後も定着しています。
また、自分が部長として場を仕切ると発言が偏るため、あえて設計だけ行い、実際のファシリテーションは部下に任せました。自分は議論に深く入らず「中立の観察者」として立ち回ることで、会議全体が変わっていきました。
学びを経て「自分が決めなければならない」という意識から「みんなの力を引き出すことが重要だ」という姿勢へと変わりました。
これからフィンランド式ファシリテーション®を学ぶ方へメッセージ
フィンランド式ファシリテーションは、必ずしもプロのファシリテーターになるためだけの学びではありません。マネジメントやチーム運営、日常の小さな場面でも、人と一緒に物事を進めるときに役立つスキルです。
会議や話し合いに課題を感じている方は、ぜひ一度学んでみてください!
世界の見え方が変わり、会議や対話の場が楽しみになると思います!
インタビュー動画紹介
企業内活用事例
損害保険ジャパン株式会社にて実施された部門パーパス策定での活用事例をご紹介いたします。
損害保険ジャパン株式会社 千葉保険金サービス部 部門パーパス策定でメンバーの主体性と一体感が向上!
一緒に、組織の中に眠る力を見つけ、未来を描く一歩を踏み出してみませんか?
私たちは、その伴走者として、丁寧にサポートいたします。


