認定ファシリテーター活用事例:北原佑介さん
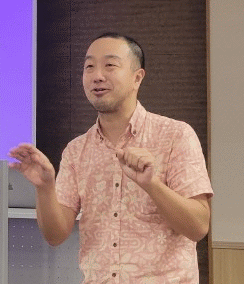
「結果に介入せず場を信じる」というあり方は、医療や教育の現場でも大きな意味を持ちます
北原佑介さん
Yusuke Kitahara
たのはたラボ代表
研修講師/ワークショップデザイナー/救急医
プロフィール
救急医として臨床に携わった後、教育・研修分野に活動を広げ、現在は研修講師・ワークショップデザイナーとして独立。医療者や多様な組織を対象に、主体性を育む研修やワークショップを提供している。
こんな場で使っています
被災地での医療支援(能登半島地震2024年)
能登半島地震の医療支援現場で、医療チームの一員として四つの質問(事実・感情・意味・行動)を活用した対話の場を実施。混乱の中で各メンバーが抱える思いや不安を言葉にすることで、チームに落ち着きとつながりが生まれました。
CSAモデルをベースにした対話の流れを使うことで、ファシリテーターが仕切らなくても自然に声が引き出され、現場のリーダーシップにも良い影響がありました。
研修・ワークショップでの活用
研修やワークショップでも、四つの質問やCSAモデルに加えて、「フェールメーター」を用いたエネルギーの可視化を活用。個人で考え、グループで共有するステップを通じて、参加者が自然に気持ちや意見を言語化でき、場の状況や心理的安全性を捉えるのに役立ちます。これにより、理解や納得感が深まり、主体的な学びや相互理解を促す場が生まれています。
フィンランド式ファシリテーション®を学んだきっかけ
独立直後に多くの学びを求める中で、信頼する仲間からフィンランド式ファシリテーションを紹介されたことがきっかけでした。当初は「フィンランド」という言葉の響きに惹かれ、直感的に学びを始めました。学んでいく中で、ツールの力だけではなく、あり方を大切にする姿勢に強く共感しました。
フィンランド式ファシリテーション®とは
一人ひとりの意見を大切にし、声の小さい人の声も取り残さない。そのために「ME-WE-US」のプロセスや「4つの質問」などのシンプルかつ効果的なフレームが活用できます。特に「結果に介入せず場を信じる」というあり方は、医療や教育の現場でも大きな意味を持ちます。
実際の活用シーンと変化
研修やワークショップの場では必ず「一人で考える時間」を設けています。これにより、普段あまり発言しない人の声も自然に引き出され、参加者全員の主体性が育まれます。また「4つの質問(事実・感情・意味・行動)」を活用して学びを深め、参加者が自分の行動に結びつけられるようデザインしています。
さらに、被災地支援の現場でもフィンランド式を実践しました。避難所を巡回する医師や保健師チームに新しい方針を伝える際、単に説明するのではなく「4つの質問」で考えを書き出し、チームごとに対話してもらいました。その結果、不安や疑問が率直に出され、単なる一方通行の伝達では得られない信頼関係や納得感が生まれました。この経験から、フィンランド式は災害支援のような緊急現場でも有効であると確信しています。
これからフィンランド式ファシリテーション®を学ぶ方へメッセージ
フィンランド式ファシリテーションは、ただの進行技術ではなく、あり方そのものを学ぶ実践です。書籍や説明で理解できる部分もありますが、実際にワークショップに参加して体験することで初めて、その深さが染み渡ります。順番を気にせず、ぜひ一度どのコースからでも参加してみてください!
体験を通じて、自分自身の学びも広がり、場のあり方が大きく変わることを実感できると思います。
インタビュー動画紹介
一期生・溝江直樹さんと三期生・北原佑介さんへの合同インタビュー動画をご紹介します。フィンランド式ファシリテーションの魅力に迫り、そのメソッドが具体的にどのような場面で活用されているのかを掘り下げています。
続く後編では、能登震災における活用事例、大規模な研修現場での具体的な実践例など、貴重なお話をじっくり伺っています。
一緒に、組織の中に眠る力を見つけ、未来を描く一歩を踏み出してみませんか?
私たちは、その伴走者として、丁寧にサポートいたします。


