認定ファシリテーター活用事例:石田克英さん
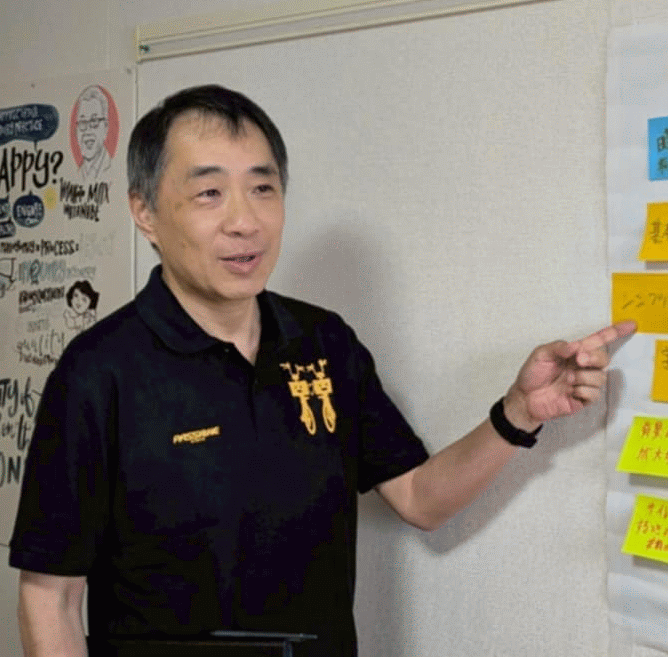
まず自分で考える時間(ME)を取ることで、普段あまり話さない人でも意見を言いやすくなり、全員の頭が同時に動く状態を作ることができます
石田克英さん
Katsuei Ishida
電子部品製造会社
開発研究所 開発企画部 次長
プロフィール
電子部品製造会社の開発研究所開発企画部 次長として、人材活性化や研究所の教育企画を推進。人材育成の一環としてファシリテーションに取り組んでいます。
こんな場で使っています
若手研究者の意見・アイデアを引き出す場
「普段あまり発言しないメンバーも、自分の考えを安心して出せる場ができるんです」開発研究所では専門性の違うメンバーが集まるため、議論がどうしても一部の人に偏りがちでした。フィンランド式ファシリテーションを取り入れることで、まず個人で考え、それを小グループで共有する時間を設けることで、声の小さいメンバーの意見も自然に出るようになりました。結果として、チーム全体で課題を整理したり、新しいアイデアを生み出す議論が活発になっています。
会議やプロジェクト運営での活用
「議論のプロセスを整えるだけで、アイデアがスムーズに集まるし、意思決定も早くなるんですよ」ホワイトボードや共有資料を使い、専門知識に関係なく議論の焦点が明確になるよう工夫しています。プロセスを重視することで、会議の効率が上がり、プロジェクトの進行もスムーズになっています。
チーム全体の創造性や改善活動に
全員の意見を丁寧に引き出すことで、従来は見えにくかった課題やニーズが表面化します。「フィンランド式ファシリテーションは、単なる会議進行じゃなくて、チームの集合知を引き出すための道具ですね」多様な意見を尊重する文化が育ち、チームの創造性や改善策の精度も高まっています。
フィンランド式ファシリテーション®を学んだきっかけ
研究所は会社の中でも最もイノベイティブであるべき組織であり、イノベーションにはコミュニケーションが不可欠だと感じていました。最初はプレゼンテーションやコーチングから始め、次のステップとしてファシリテーションが必要だと思ったのが学びのきっかけです。
これまでにもMBAや研修会社、ファシリテーション協会などで学んできましたが、フィンランド式は特にビジネス課題の解決に有効だと感じ、さらに学びを深めることにしました。
フィンランド式ファシリテーションとは
研究開発の現場では個性が強く意見を主張する人もいれば、普段は黙っている人もいます。フィンランド式は、まず自分で考える時間(ME)を取ることで、普段あまり話さない人でも意見を言いやすくなり、全員の頭が同時に動く状態を作ることができます。
これは「集合天才」という考え方に通じており、一人の発想ではなく、複数の専門性を持った人たちが一緒に考えることで、新しい価値を生み出すことができる仕組みだと思います。
実際の活用シーンと変化
研究開発の会議やプロジェクトのアイデア出し、若手メンバーとの課題解決の場で活用しています。特に若い世代には合っていて、「短時間で課題解決ができる」「意見を言いやすい」と好評です。
また、声の大きな人の発言が場を支配してしまう会議でも、フィンランド式を取り入れるとバランスが取れ、普段は意見を言わない人からも良いアイデアが引き出されるようになります。さらに「MEの時間を宿題にする」といった工夫を加えることで、議論が一層深まることもありました。
これからフィンランド式ファシリテーション®を学ぶ方へメッセージ
まずは学んで使ってみることが大事です。フィンランド式はシンプルなやり方なので、誰でも実践できます。自分自身の能力を高めるだけでなく、その場全体の課題解決能力を底上げしたいと考えている方には特におすすめです!
認定試験を通して感じたことは、基本に忠実に、そしてシンプルに実践することが一番効果的だということでした。学んだことを現場で活かし、繰り返し実践することで、必ず大きな成果につながると思います!
インタビュー動画紹介
一緒に、組織の中に眠る力を見つけ、未来を描く一歩を踏み出してみませんか?
私たちは、その伴走者として、丁寧にサポートいたします。


